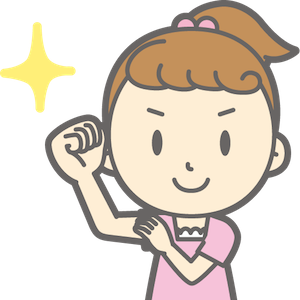
休憩時間でリフレッシュして、勉強の集中力アップ。

メニュー

|

|

|
障害を持つ小学生、休憩時間のリフレッシュで勉強効率が全然違う。

休憩時間を上手に使おう。
勉強の合間のリフレッシュ方法は、障害児の勉強効率を大きく左右します。
上手に休憩時間を活用すると、勉強の効果がアップ。
反対に、だらだら休憩してしまうと、勉強を再開しても全く身につきません。
テレビ、ゲーム、音楽と、発達障害児の勉強方法。
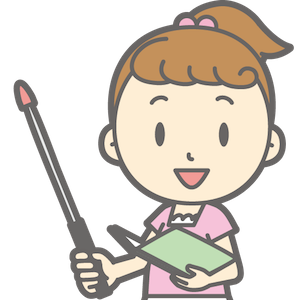
勉強の息抜きは、時間を決めて。
勉強の休憩中に、テレビを見る、ゲームをする、これは悪いことではありません。
時間を決めてリフレッシュできるなら、勉強にプラスになります。
だらだら、テレビを見てしまう。
だらだら、ゲームをしてしまう。
これは勉強の大敵です。
テレビとゲームは、親子でルールと時間を決めましょう。
勉強の息抜きは、脳を休めて、体を動かすのがベスト。

勉強の合間は、体を動かし、脳を休める。
- 脳を休めること。
- 体を動かすこと。
勉強の合間の休憩では、これがベストです。
休憩で疲れた脳をリフレッシュして、また次の勉強に集中する。
勉強中は体を固定して、じっとしているので、休憩時間に体を動かすこと。
- 親子で楽しく会話する。
- 体操で体を動かす。
- 好きな音楽を聴く。
こんなことで、心身ともにリフレッシュ、気持ちを切り替えて、勉強を再スタートする工夫をしましょう。
休憩時間に、テレビやゲームでも時間を決めてやれば悪くはないですが、ゲームに集中してしまうと、脳が疲れてしまいます。
勉強の合間に外に出てみる。
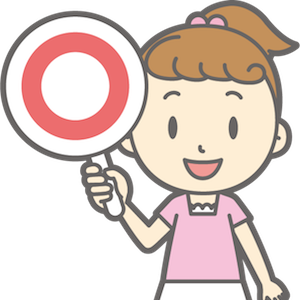
気分転換に外出もOKです。
勉強の休憩時間には、家の外に出てみると、気分転換になります。
小学校では、午前中の授業の合間には「中休み」、昼には「昼休み」があり、小学生が気分転換をしながら、授業を受けられる工夫があります。
家庭での学習の休憩は、ついつい部屋の中で過ごしてしまいますが、親子で5分だけでも外に出てみると、リフレッシュ効果が絶大です。
- 5分間、散歩する。
- 5分間、庭で外の空気を吸う。
これだけで、家の中に閉じこもった休憩より、リフレッシュした気持ちで、勉強を再スタートできます。
静かなクラシック音楽でリラックス。

クラシック音楽で、リラックス。
勉強前や、勉強の合間に、静かなクラシック音楽を聴いて、リラックスする。
静かすぎる部屋で勉強すると、近隣の雑音が聞こえて、かえって気が散る場合があります。
静かなクラシック音楽をBGMとして聴きながら、勉強するのも、他の雑音を遮る効果があり、集中力がアップします。
ただし、激しい音楽は、集中力を乱します。
心を落ち着かせる、静かなクラシック音楽を選曲しましょう。
テレビの教育番組を活用する。
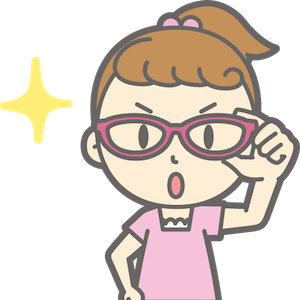
NHKのEテレ、教育番組も視覚的な勉強に効果があります。
NHK教育テレビの、小学生向けの算数の番組は、面白くて、内容も分かりやすい。
「さんすう犬ワン」は、小学1年から3年生までの低学年向けの算数番組。
「さんすう刑事ゼロ」は、小学4年から6年生までの高学年向けの算数番組。
どちらもドラマ風に算数の課題を、面白く、楽しく、子供が理解できるような、テレビ番組です。
障害を持つ子には、視覚的な情報を活用した勉強方法が有効です。
教科書だけで勉強するより、動きのあるアニメーションで解説してくれた方が、理解度がアップして効率的に勉強ができます。
勉強が苦手な障害を持つ子は、教育テレビの番組を、絶対に活用しましょう。
歴史、動物のテレビ番組も、勉強に興味を持つきっかけに。
小学校6年生になると、社会科で歴史の勉強が始まります。
母親が、大河ドラマなどの歴史ドラマを見ながら、子供が歴史の勉強に興味を持つように、誘導してあげましょう。
動物や昆虫は、理科の勉強です。
動物のドキュメンタリー番組、昆虫の番組も、親子で楽しみながら、勉強のきっかけになります。
まとめ、発達障害児の勉強方法、テレビ、ゲーム、音楽。

上手に休憩すれば、集中力が持続して、効果的に勉強できます。
- 勉強の息抜きは、時間を決めること。
- 脳を休めて、体を動かすのがベスト。
- 勉強の合間に外に出てみる。
- 静かなクラシック音楽でリラックス。
- テレビの教育番組を活用する。
- 歴史、動物のテレビを、勉強に興味を持つきっかけに。
休まず勉強を続けられればいいのですが、障害を持つ子は、適度な休憩がないと、集中力が続きません。
上手に子供をリフレッシュさせて、勉強の効率をアップさせましょう。
メニュー

|

|

|





