
予習と復習をして、授業中にノートを取らない勉強方法です。

メニュー

|

|

|
予習と復習で、授業中はノートを取らない。

予習と復習は、障害児の勉強のポイントです。
発達障害児や知的障害児は、学校の授業だけでは、勉強の内容を理解できません。
そのため、家庭でしっかり予習と復習をすることで、授業の内容を理解し身につけることができます。
予習と授業と復習で、3回勉強できる。発達障害児の勉強方法。
予習で、わからない内容をチェック。
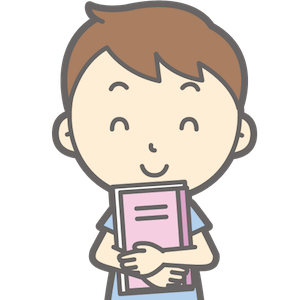
予習しなくて、いきなり授業じゃ理解できない。
学校の授業は、勉強が得意な子、勉強が苦手な子、全員一緒に教えています。
予習をしなくて、いきなり学校の授業だと、勉強が苦手な障害を持つ子は、授業のペースについて行けません。
勉強が苦手な子でも、授業のペースについて行くために、予習をやるのです。
予習の段階では、勉強の内容がわからなくても、気にしません。
障害を持つ勉強が苦手な子は、1回予習をしたくらいでは、勉強の内容を理解できません。
予習では、わからない勉強内容はどこかを確認するだけと、割り切って考えましょう。
1回の予習でわからなくても、学校の授業と、その後の復習と、もう2回勉強する機会があります。
学校の授業、聞くに集中、ノートは取らない。

ノートが苦手なので、先生の話だけに集中する。
授業中に、先生の話を聞きながら、ノートを書き写す。
勉強ができる子は、当たり前にやっていることです。
発達障害や知的障害を持つ子は、複数のことを同時にやるのが苦手です。
ノートに書き写すことが苦手な障害を持つ子は、書くだけで精一杯になります。
先生の話を聞く余裕が無くなります。
- ノートに書き写すこと。
- 先生の話を聞くこと。
この2つで、どちらが重要かと言うと、「先生の話を聞くこと」です。
勉強の内容を先生が説明してくれる時には、ノートを取らずに、先生の話に集中した方が、効率よく勉強ができます。
ノートを取らずに、先生の話を聞くだけ。
そう割り切れば、複数同時が苦手な発達障害児でも、授業に集中できるようになります。
その日のうちに早めに復習、忘れる量が少なくなる。
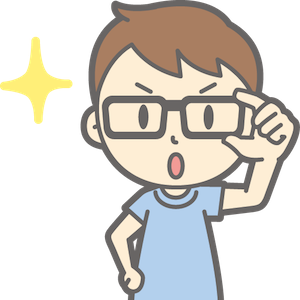
復習で覚える。
復習は、学校の授業で習った、その日のうちにやると、効果があります。
人間は、その日に勉強したことの70%を、次の日には忘れてしまいます。
その日に、すぐ復習をすることで、忘れる量が少なくできます。毎日、毎日、繰り返し復習することで、勉強の記憶は完璧になります。
ただでさえ、発達障害児や知的障害児は、忘れやすいものです。
短時間でのいいので、その日のうちに必ず授業の復習をしましょう。
宿題で、授業を効率的に復習。

しっかり宿題をやる。
学校の宿題は、その日の授業で習った勉強内容がほとんどです。
つまり、宿題をやれば、授業で習った勉強内容を、復習できるんです。
私は、うちの子に学校の宿題が出たら、授業の復習は、宿題だけにします。
担任の先生が、これをやれば授業の復習になる、そう考えてくれた内容が宿題ってことですから。
子供に宿題をやらせても、わからない内容は、もう一度教科書を見直すこと。
予習と学校の授業、2回も勉強して、まだ宿題でわからない内容の勉強なら、基礎から勉強のやり直しが必要です。
障害を持つ勉強が苦手な子には、何度やっても、できないことがあります。宿題ができなくて子供を叱っても意味がありません。
家庭での予習、学校での授業、家庭での復習、この繰り返しが発達障害児の勉強方法

予習、授業、復習、この3つの繰り返し。
勉強ができる子は、予習、授業、復習、このどれかが欠けても、勉強を理解ができます。
全然、家庭で勉強しなくても、学校の勉強ができる子がいるのは事実です。
しかし、障害を持つ勉強が苦手な子は、
- 家庭での予習
- 学校での授業
- 家庭での復習
この3つを繰り返さないと、勉強ができるようになりません。
時間と労力がかかりますが、努力して勉強すれば、ちょっとずつ、前進できます。
まとめ、発達障害児の勉強方法、予習、授業、復習の繰り返し。
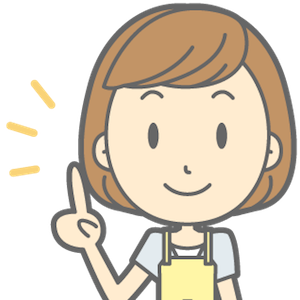
障害を持つ子は、学校の授業をメインで、家庭で予習・復習しましょう。
- 予習で、わからない内容をチェック。
- 学校の授業、聞くに集中、ノートは取らない。
- その日のうちに早めに復習、忘れる量が少なくなる。
- 宿題で、授業を効率的に復習。
家庭での予習、学校での授業、家庭での復習、この繰り返しが発達障害児の勉強方法の基本です。
学校の授業を中心としつつ、家庭での予習と復習で挟み込みましょう。
メニュー

|

|

|





