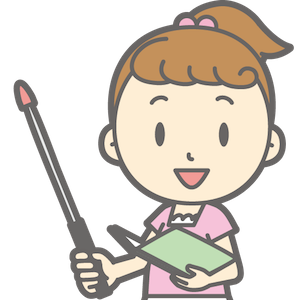
作文が必ず書けるようになる、3つの勉強方法です。

メニュー

|

|

|
障害を持つ子は作文が苦手。

作文が苦手です。
障害を持つ子は、作文が苦手な場合が多いです。
自分で考えた内容から、文章を構成しながら、文字として書く、これが作文です。
障害を持つ子は、文章を読むことができても、自分で文章を作る、作文ができない場合が多いのです。
この作文を、上手に書けるようになる3つの勉強方法です。
1、日記を書く。
作文が苦手な子が、作文を勉強するために、まずは、日記を書かせましょう。
初めは、親子のおしゃべりの言葉を、そのまま文として日記に書かせます。
例えば、お母さんと子供で、学校での出来事を話している言葉を、そのまま日記として、子供に書かせるのです。
日記の書き出しの言葉を、「お母さん、あのね。」と、おしゃべりするような言葉にすると、子供が文章を書きやすくなります。
絵日記でもOK。

絵を書くのは好き。
日記を書くのが難しいようなら、絵日記でも構いません。
まず、絵を描いて、その内容について、短い文章の日記を書きます。
日記でも、絵日記でも、自分の思ったことを書くことが、作文の勉強になるので、子供が楽しく続けられる方法にしましょう。
植物や昆虫の観察日記でもOK。
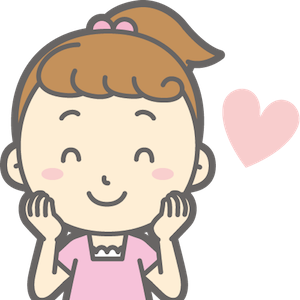
お花も大好き。
お花が好きな子には、お花の観察日記。
昆虫が好きな子には、昆虫の観察日記。
日常の出来事の、普通の日記じゃなくても、子供が興味を持つことの観察日記での構いません。
観察日記で、植物などを学習すれば、作文の勉強だけでなく、理科(生活科)の勉強にもなります。
2、親が質問をしてあげる。

お母さんとの会話が、ヒントになる。
作文が苦手な子の文章は、やったことを羅列になりがちです。
親子の会話から、その時に感じた気持ちを引き出して、感情を文章にできるように誘導してあげましょう。
例えば、
「今日、昼休みに外あそびをしました。おにごっこをしました。楽しかったです。」
この作文に対して、
「外は暑かった?寒かった?、走った後は汗をかいたんじゃない?、終わった後のみんなの様子は?」
と、親が質問をして、その回答内容を作文に書かせます。
「今日、昼休みに外あそびをしました。おにごっこをしました。
外は寒くて風が強かったけど、走った後は、体が熱くて汗が出ました。
クラスみんなで遊んだ後は、いつもよりみんなの笑顔が多くなって、楽しかったです。」
親が質問をすることによって、やったことの羅列から、感じたことや、周りの様子などを、書けるようになります。

会話から、気持ちを引き出せば書ける。
3、良い作文を書き写す。

文章の表現方法を真似して覚える。
自分で考えて作文が書けない子には、良い作文を書き写しながら、文章の構成を勉強させましょう。
国語の教科書には、作文の教材があります。
教科書の作文教材は、文章の構成や、表現方法などが、それぞれの学年にふさわしく、参考にするには最適です。
お経を書き写す「写経」のように、教科書の作文教材の繰り返し、書き写すことで、その文章の意味を深く読み取り、自分の表現として作文がかけるようになります。
作文を書き写す時に、意識するポイントがあります。
子供が作文を書き写す時に、このポイントを教えましょう。
- 「やったこと」「見たこと」「聞いたこと」という客観的な文は何か?
- 「思ったこと・考えたこと」という主観的な文は何か?
- 「はじめ」「途中」「終わり」や「起承転結」という順番
- 会話が「カッコ」で書かれているか?
客観的な出来事に、誰かの会話や、自分の考えた感想を加えると、生き生きとした表現の作文がかけるようになります。
まとめ、作文が書ける勉強方法
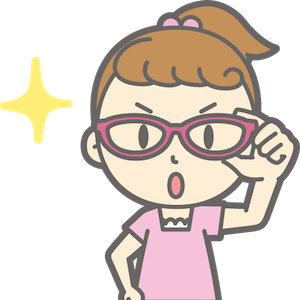
作文が苦手でも、必ず作文が書けるようになる、3つの勉強方法です。
- 1、日記を書く。絵日記でも観察日記でもOK。
- 2、親が質問をしてあげる。気持ちを引き出す。
- 3、良い作文を書き写す。文章の表現方法を真似して覚える。
ポイントを押さえた勉強方法なら、障害を持つ子でも、必ずできるようになります。
メニュー

|

|

|





