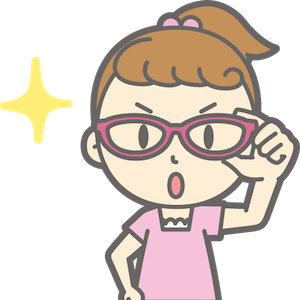
学習効果が高い時間に、集中して勉強。

障害を持つ小学生の母親、私の悩み。

発達障害を持つ子、知的障害を持つ子が、無理なく、上手に勉強に取り組むには、何が大事なのか。
勉強が苦手な障害児が、勉強するには、普通に学校に行って、普通に宿題をやらせるだけじゃ、不十分です。
学校の授業が理解できない、授業に集中できない、宿題がわからない、こんな発達障害児や知的障害児の勉強では、母親のサポートが絶対に必要です。
メニュー

|

|

|
脳科学を活用、障害児を持つうちの子が勉強する時間
朝起きてから2〜3時間後に勉強する。
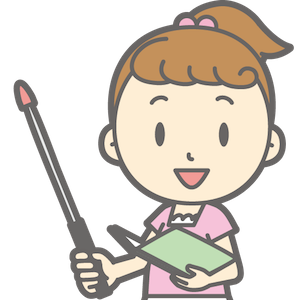
脳科学で有効な時間に勉強して効率アップ。
人間の脳が活発に働くのは、起きてから2時間経ってからです。
脳の働きが一番いいのは、起きてから2〜3時間後だと「脳科学」で判明しています。
つまり、この時間に勉強をやるのが、一番効率的だということ。
起きてすぐの脳で勉強するのは、非効率。朝起きたら、親子で散歩やジョギングして、楽しくリラックス。
脳が働く時間に合わせて、勉強を開始すれば、短時間で効率的に勉強ができます。
勉強時間が同じなら、脳が活発な時間に勉強した方が、効率的なのは当たり前です。
夜ふかしは、勉強の効果がダウン。
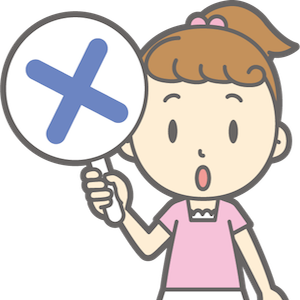
夜更かしの勉強はダメ。
睡眠は脳をリフレッシュします。小学生の睡眠時間は、8時間以上が目安です。
夜更かしして、寝不足だと、脳の働きが鈍くなり、勉強しても効果がなくなります。
早く寝て、8時間睡眠、そして早く起きる。
頭をスッキリさせてから、勉強することで、同じ勉強量でも、効率が全然変わってきます。
夜遅くまで勉強するのは、小学生のうちは、やめておきましょう。
毎日の生活のリズムを身につける。

早寝早起きの生活のリズム。
勉強は、一日だけやっても、効果がありません。
毎日の繰り返しが重要。
規則正しい生活で、継続して勉強する。
そのためには、毎日の生活のリズムを身につける必要があります。
早寝早起きの習慣、自分の家族にあった生活の時間を見つけて、子供の勉強効率をアップしましょう。
我が家は、朝5時30分に起きて、夜は20時に寝ています。
学校が休みの休日でも、同じ時間に起きて寝るようにして、生活のリズムを守っています。
発達障害児、知的障害児には、勉強をする環境作りが大切です。
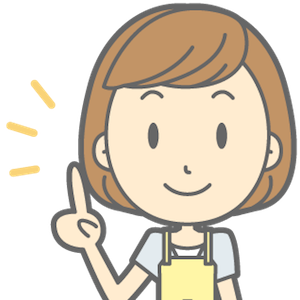
障害児の勉強方法では、勉強をする環境作りが大切です。
発達障害や知的障害を持つ子は、ただでさえ勉強が苦手です。
無理に勉強させても、効果はあまりありません。
しかし、障害を持つ子でも、コツをつかんで、繰り返し勉強をすれば、必ずその子なりには進歩できます。
たとえ、障害のない子に比べて、圧倒的に成績が良くなくても、障害を持つ子自身が、努力して勉強が楽しいを感じられれば、十分だと思いませんか?
小学校で習う勉強の内容は、大人になっても、日常生活で役に立つ、とても面白い知識がたくさんあります。
勉強がわかるようになれば、発達障害や知的障害を持つ子でも、どんどん勉強に対して、興味や意欲がわいてくるはずです。
障害児の勉強方法では、勉強をする環境作りが大切です。
障害がない子に比べて、問題の解き方や、暗記方法だけではなく、勉強を始める前の段階が重要なんです。
勉強する場所の整理整頓、テレビとの関わり方など、集中して勉強ができる環境作り。
そして、早寝早起きで頭をスッキリさせる、朝ごはんをしっかり食べて脳の働きを良くする、脳科学の根拠に基づいた、勉強ができる体調管理方法。
これらの、間接的な勉強方法も、発達障害児や知的障害児に、特に有効です。
まとめ、発達障害児の勉強時間のポイント

脳科学で、効率的に勉強しよう。
発達障害、知的障害を持つ子が、勉強を頑張るためには、勉強する時間を工夫する。
そうすると効率よく、勉強ができます。
- 朝起きてから2〜3時間後に勉強する。
- 夜ふかしはしない、勉強の効果がダウン。
- 小学生のうちは、睡眠時間は8時間以上。
- 毎日の生活のリズムを身につける。
メニュー

|

|

|





