
時間や長さ、重さ。抽象的なことが苦手。
メニュー

|

|

|
小学2年生、抽象的な概念が理解できない、学習障害LDの発達障害児の勉強方法。

小学校2年生。のんびりしてます。
小学2年生のちょっとのんびり&おとぼけ気味の女の子を持つ、42歳の母です。
現在の仕事は、朝8時半から昼3時半までの進学予備校のパート勤務です。
この仕事を始めて4年目になります。
母親である私の性格は、子どもとは正反対で、何事もささっとしないと気がすまない&身近な天然ボケ気味な人に、イラっとしてしまうような、ちょっと冷めた人間です。
教育関連の仕事についていますので、わが子の出来なさ加減が、それはそれはよぉ~くわかります。
時計の問題、単位の問題、抽象的なことが理解できない。

算数の時計や単位の問題ができません。
小学2年生の娘は、特に算数が苦手でその中でも時計の問題、単位の問題がヤバイくらいにできません。
この手の問題はもう感覚というか、それまでの実体験を通して身につくと思うのですが、いかんせん、わが子は、のんびり&おとぼけ気味なため、時間感覚や、量や長さの感覚というものが、全く身についていません。
というかそのようなものに関心がない、といいましょうか。
いつもマイワールドにひたっています。
2歳年下の妹の方が、かえって時間感覚がしかっり身についています。
それゆえ、このままではマズイと思い、あれやこれやと試してきました。
目盛りのついた時計を購入。
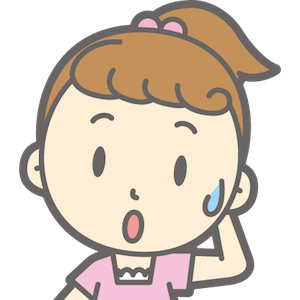
目盛付きの時計。
まず一つ目に試したのは、教育用の細かい目盛りのついた時計の購入です。
購入当時は興味を持ってさわったりしていましたが、効果なし。
同時に妹にも買いましたが、妹は毎朝その時計で目覚ましをセットし、自分で起きるのですが、小学校2年生の当の本人は全く使用する気なし。
時間感覚が身につけばと、淡い期待をもっていましたが、見事に打ち砕かれています。
高価な算数の教材、イマイチ活用できない。
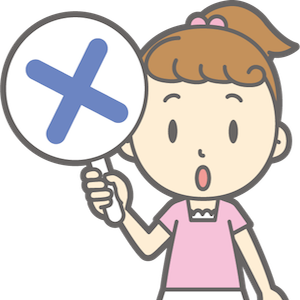
算数の教材シリーズ。
二つ目は某新聞広告に掲載されていた、遠山啓著のさんすうの本のセットです。
1冊2000円以上する高価な本が、シリーズになっています。
小学1年生から6年生までのさんすうの勉強が、系統立ててわかるようになっているであろう、セットの本なのですが、イマイチ活用しきれていません。
さんすうを理解するための助けになる、お話しになっているのですが、いかんせん文字が結構多いので、子どもにとっては読みにくいようです。
いつか自ら手にとって読んでほしいと願いを込めて、リビングの目につくところにいまだに置いてあります。
タブレット学習教材、国語や英語には学習効果あり。

使いやすいタブレット教材。
三つ目はタブレット学習です。
スマイルゼミです。
学校で使用されているデジタル教科書のように、時計が動いたり、水のかさなどが目で見てわかりやすいように工夫されているので、これは期待できると思って申し込みましたが、学習の記録をながめていると、どうやら苦手意識のある算数はあまりやらず、国語や英語ばかり繰り返しやっていた、ということがのちに判明いたしました。
国語と英語の勉強では成果が出たのは事実なので、このスマイルゼミは続けますが、肝心の算数では、成果が出ませんでした。
やっぱり母親の私が、勉強を見てあげるしかない。
ひとえに子供が算数を得意になってくれるようにと願って、この3つのお金の無駄遣いの経験からわかったことは、何かに頼ってはいけない、ということです。
子どもが宿題をしているときは家事の手を止めて、終わるまでじっくりと見てあげる、自主学習の問題を書いてあげる、わかりやすいような単位の表を目に付くところに貼っておくなど、自分の時間を割いて子どもと向き合うことが一番大切なのではないか、と思い至りました。
我が家は3姉妹なのですが、この小2の子は発達障害があるので、長女や三女と違って、目をかけてあげなくてはならない子なんだ、という認識をもって接するようにしています。
メニュー

|

|

|




